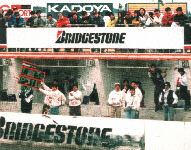  |
|
| RZチューニング ワンポイントアドバイス | |
| RZを代表するヤマハの2ストロークマシン(RD・RZR等)は、TZレーサーの流れを組むロードスポーツであり、チューニング(カスタム)する場合には一般的な常識や他のマシンの手法とはまったく違った考え方が要求されることがあります。 ここでは弊社が多くのマシンを製作する中で学んだことを紹介します。 |
Last Up Date : Apr-00
RZ Tuning
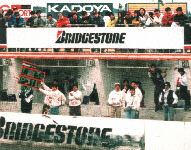  |
|
| RZチューニング ワンポイントアドバイス | |
| RZを代表するヤマハの2ストロークマシン(RD・RZR等)は、TZレーサーの流れを組むロードスポーツであり、チューニング(カスタム)する場合には一般的な常識や他のマシンの手法とはまったく違った考え方が要求されることがあります。 ここでは弊社が多くのマシンを製作する中で学んだことを紹介します。 |
| フロントフォーク | |
| 初期型のRZに関して言えば、フロントフォークは硬くすべきではありません。しなやかなフォークから生まれるハンドリングを最大限に引き出すためには、どれだけスムーズに動かすことができるかを考えるべきです。そのためにはスプリングも強化すべきではないと思いますし、オイルの粘度すら硬くすべきではないと思います。ブレーキングで沈み込みが大きい?それはオートバイにとってはごく自然な現象なのですから、無理に抑えるべきではないのです。 とにかく柔らかくし、そして不具合が出たときに少しずつ硬くしていく方向で仕上げていくと良いでしょう。ちなみに91年に筑波サーキットで行われたMCFAJのプロダクションスーパーでRC30やGSX−R750を抑えて優勝した弊社の初期型RZ350の場合、足回りは完全にノーマル。(フォークはノーマルスプリングにヤマハ純正の5番オイルを使用)オイル量のみを調整してセッティングしました。 |
|
| タイヤ | |
| タイヤは多くの人が考えている以上に重要な部品です。その銘柄やパターンでオートバイのハンドリング、性格は激変してしまいます。ハンドリングに不満が出たら、まずタイヤを変えてみて下さい。初期型RZでノーマルホイールを使用する場合、ダンロップのTT100を推奨します。ただし、このタイヤはフロントのサイズに注意が必要です。90/90−18というサイズを選択することが多いようですが、本来の純正サイズである3.00−18を装着することでフロント周りの動きが極めて自然になり、RZ本来の俊敏な操縦性を現代に再現できるのです。RZが現役だった当時の高性能タイヤが、最もマッチングが良いのは、考えてみれば当然のことなのです。 より高いグリップを求めるならダンロップのGT501やBSのBT39、グリップを最優先するならダンロップのTT900でしょう。これらのタイヤは剛性が高いため、空気圧を低くするなどしないと高速コーナーでチャタリングに悩まされる可能性があります。しかし、こういった点を対策できれば、想像以上のパフォーマンスを発揮することができるでしょう。細いタイヤが不安だと言って、ワイドリムを装着する例を良く見ますが、タイヤは太さでグリップするのではありません。RZの俊敏な操縦性は適正なサイズでのみ発揮されるということを覚えておいて下さい。 |
|
| ブレーキ | |
| RZのブレーキは効かないという話を良く聞きます。しかし、決してそんなことはありません。少なくともノーマルのダブルディスクならサーキット走行でも支障がないくらいの制動力を発揮させることができます。まずはノーマルのブレーキを徹底的にオーバーホールして下さい。キャリパーのピストン・シールはもちろん、スライドピンの汚れも完全に落としてスムーズに動くようにし、さらにマスターシリンダー内部パーツを全て交換します。スポンジのようなタッチはステンメッシュホースの使用と完全なエアー抜きで改善できます。パットは高性能のものを選び、装着前にヤスリでアタリを取ってから組み付けて下さい。ロッキードやブレンボなどの硬質なタッチがほしい場合は、これらの高性能キャリパーをシングルで装着することで、ダブルディスク並みの効きとシングルディスクのバネ下を得ることができるでしょう。高性能なブレーキを装着することは簡単ですが、バネ下重量の増加によりハンドリングは確実に低下してしまいます。間違ったパーツチョイスをしてしまうと必要のない制動力アップのために、重要な性能を低下させることになりますので、十分に注意して下さい。 | |
| エンジン | |
| ストリートを走るならば特にチューニングを行う必要はありません。給排気系だけの変更でRZは十分なパワーを発揮します。2ストロークエンジンに関しての豊富なノウハウがあるならともかく、通常はポート加工や圧縮比をアップさせたエンジンよりも、ノーマルをこまめにメンテナンスしたエンジンのほうが扱いやすく、また速いというのが普通なのです。 | |
| メンテナンス | |
| レーサーなら走行毎に、ストリートなら2000km毎程度でシリンダー、ピストンの磨耗状況の確認、キズがあれば修正、ピストン&ヘッドのクリーニング、クランクのガタなどをチェックすることをお勧めします。この時シリンダーやピストンに小さなキズがついている場合(特に初期型)、800番程度の耐水ペーパーで斜めにクロスハッチを入れるように磨いて落とすことを忘れないで下さい。 | |
| キャブレター | |
| レース用であればφ32〜38mmのキャブレターを装着します。ミクニ、ケイヒン共に高性能であり、それぞれ高い実績を残していますので好みで選んで良いでしょう。マニホールドは他車種用を加工しても取り付けはできますが、思わぬ不具合が発生することがありますので当社製品を推奨します。リードバルブは350Rならば初期型TZR(1KT)用を加工して使用することもできます。初期型RZや250R、RD400の場合はノーマルのリードケースでバルブのみを交換するか、もしくは吸気ポート入口を拡大して350R用を使用することができます。 RZの場合はキャブレターの大きさによる特性の違いは出にくいようですが、形式の違いははっきり出ます。例えばミクニ製TMX38の場合、鋭いレスポンスが最大の特徴になります。また同じミクニでもVMタイプは扱いやすいレスポンスと安定した性能が得られます。中間特性は大きく異なりますが、最大出力では大きな差は出にくいようです。ケイヒンではPWKが良いでしょう。時々TZ用のTM38やRS用のPJを流用しているケースを見かけますが、当社ではあまりお勧めしません。 RZはキャブレターの交換による効果を感じにくいオートバイですが、例えば口径を大きくしてもパワーフィーリングがまったく変化しない場合は、マフラーの性能が追いついていないことがあります。パワーの要であるチャンバー容量が少ないと、いくらキャブレターを大きくしてもパワーを出すことはできません。 ストリートの場合はキャブレターはノーマルでも十分なパワーを得ることができます。例えばエアクリーナーのカバーは付けたままで、エレメントのみを取り外し、メインジェットを10%程度増やすだけで、ずいぶんフィーリングが変わります。パワーフィルターを装着しても同様の効果を得ることはできますが、キャブレターからはオイルを含んだガソリンが吹き出すため、すぐにフィルターが詰まるので、こまめにメンテナンスする必要があります。 |
|
| チャンバー | |
| 2ストロークのパワーの鍵はチャンバーです。極端な話、どんなにハイチューンしたエンジンに高性能キャブレターを装着したとしてもチャンバーの性能がそれに見合っていなければ、十分な性能を発揮することはできません。逆に完全にノーマルのエンジンだったとしても良いチャンバーさえ装着すれば、信じられないパワーを絞り出すことができます。 チャンバーによる特性の変わりようは凄まじく、例えば80年頃のSP忠男のフレックスやクラフトマンのチャンバーを初期型RZに装着した場合のパワーバンドは5000〜9000rpmです。ところがTZ350用を同じエンジンに装着するとパワーバンドは8500〜11500rpmにまで変化します。 RZの場合は特に中古のチャンバーを購入して装着するケースが良く見られますが、ここで注意しなければいけないことがあります。全体的な傾向として、RZ・RZR用を問わず、250用に設計された高回転型のチャンバー(SSイシイ製TZレプリカ、城北ムラカミ250用等)を350に装着した場合、回るだけでトルク感のないエンジンになりがちです。また、さらにセッティングも非常にシビアになります。これはサーキット走行でのバンク角を考えて、必要最小限の容量に設計しているためで、外観は太くて短いのが特徴です。逆に細長いタイプ(クラフトマン、SSイシイクロス、SP忠男フレックス、ノグチ等)は明確なパワーの立ち上がりと太いトルクを感じられることが多いと考えて下さい。ストリートで使う場合、その速さや楽しさを味わいたいのであれば後者をお勧めします。また、250には基本的にどちらを着けても失敗はないと思いますので、自分の好みのものを選んでください。なお、初期型RZにRZR用のチャンバーを装着すると、極端に低速トルクがなくなることがありますが、反対にRZRにRZ用を装着すると中速での素晴らしい盛り上がりを体感できることもあります。 RZとRZRは基本設計(ボア×ストローク)が同じなので、ある程度の互換性はあります。ただし、これはあくまで目安ですので、自分のマシンとの相性は実際に装着して調べるしかありません。ちなみにTZRや81年以降のTZは全く別の仕様のエンジンであり、RZ系には合いません。これらを装着してもトルクの盛り上がりを感じないまま、どこまでも回るといったフィーリングになるでしょう。 |
|
| 電気系 | |
| RZ系のマシンはストリートで使う場合、電気系のチューニングを行うことは一般的ではありません。ただし、好調を維持するために交換をお勧めするパーツはいくつかあります。RZ系はエンジンのマウント方法の違いにより、他のマシンと比べ振動が多少大きく出てしまいます。初期型に使われているようなプラグキャップはこの振動に耐えられず、プラグに差し込まれる電極部分が変形し、接触不良を起こす場合があります。このトラブルを未然に防ぐために、TZR(1KT)用に交換することをお勧めします。アフターマーケット製のプラグキャップに交換する場合は、TZR用と同様のプラグのアルミキャップを使うタイプを選んで下さい。 | |
| フレーム | |
| 弊社では基本的にフレームの補強は行っておりません。現在まで数々のレースおよびストリートの経験より、一般に弱いと言われている初期型RZでさえ、補強の必要はないと判断しているからです。マシンが振られる場合、そのほとんどはフレーム以外に原因があります。タイヤの偏磨耗やアンバランス、サスペンションの作動不良や硬すぎるセッティング、ベアリング類の作動不良などです。 RZ本来の操縦性はギリギリの強度を保っているフレームによって実現されている訳ですから、そのフレームを安易に硬くすれば、本来のしなやかな味が失われてしまうのは当然のことです。確かに高速コーナーでショックが加わったりすればマシンはユラユラと揺れますが、これは異常ではありません。必要最低限の強度によって、しなやかなハンドリングを得ているためなのです。 このような理由から弊社ではRZのフレーム補強はしていませんし、リヤ周りにリンク式のサスペンションを移植するようなカスタムも行っていません。また、タイヤのサイズアップもあまり推奨できません。 ただし、RZRの場合は話が違ってきます。乗り比べてみると分かるようにフレーム剛性はずいぶん高くなっており、最近のマシンに近いフィーリングとなっています。ですから最新の足回りを装着してもあまり違和感はでませんし、ラジアルタイヤのグリップもしっかり支えることができます。 |
|
| リヤショック | |
| RZ・RZR共に高性能なリヤショックが販売されています。純正パーツの価格が上がってしまったために、純正のリペアとして高性能なショックを選ぶ方もいるようですが、RZの場合はセッティングに十分注意して下さい。レーサーや最近のマシンのように硬くしてしまうとハンドリングが悪化してしまいます。 セッティングする場合は、まず自分の乗り方でリヤショックがボトム寸前まで動くくらいに柔らかくしてみて下さい。そこから徐々に硬くしていったほうが失敗は少ないと思います。また、RZの場合はダンピングの弱めの方が良い結果となることが多いようです。スプリングのレートやプリロードがおおよそ決まってからダンピングを徐々に強くしていって下さい。なお、基本的に調整するのは伸び側で、圧縮側は極端にサスの動きを妨げない状態で固定し、他のセッティングがほぼ決まってから、最後に硬めと柔らかめに振って、フィーリングを確認して下さい。なお、基本的にはこれも柔らかい方向にした方が失敗は少ないと思います。 |